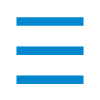日本の公立小学校での日常を追ったドキュメンタリー映画「小学校~それは小さな社会~」がフィンランドで人気を集め、海外の映画祭でも上映されるなど、国際的に注目を浴びています。
監督の山崎エマさん(35)は、「小学校を知ることは、日本の未来を考えることにつながる」と語ります。
日本の子どもたちの普段の日常の姿にカメラを向ける作品。遠く離れたフィンランドで話題になるとは想定外でしょう。
山崎さんが考える理想の小学校の姿とはどのようなものなのでしょうか。
Q&A形式でお届けします。
(※2024年12月25日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
公立小学校の制度の魅力と課題、大人に求められる進化とは
聞き役:東京・世田谷にある公立小学校で、1年間にわたり計700時間の撮影を行ったそうですが、公立小学校を題材に選んだ理由は何でしょうか。
山崎さん:私は英国人の父と日本人の母のもとに生まれ、大阪の公立小学校を卒業しました。
その後、中学・高校はインターナショナルスクールに通い、大学は米国へ進学。
ニューヨークで働く中で、「努力家だね」「責任感が強いね」「チームワークが得意だね」と評価されることが多く、自分の基盤はどこで培われたのかを改めて考えました。
その答えは、小学校の6年間にあったのです。
教科以外の時間に見えた日本の学校のリアルと日本の教育観
聞き役:教科を教える授業以外の時間に焦点を当てていますね。
山崎さん:実際に学校で見聞きし、感じ取ったリアルな姿をどう伝えられるかを考えた結果、自然と教科以外の時間が中心になりました。
撮影時期はちょうどコロナ禍と重なり、海外では1年半以上も学校閉鎖が続いた国もありました。
しかし、日本では比較的早く再開されました。
その背景には、「学びの場」としての学校の重要性があるのではないかと考えています。
教室という空間がなければ得られない学びが多く存在し、日本の教育における価値観や優先順位が、他国とは異なるのではないかと感じました。
日本の教育の強みと課題を考えるきっかけになれば・・・
聞き役:日本では、いじめや不登校の問題が議論され、フリースクールを選ぶ家庭も増えていますね。
山崎さん:これらの課題についても考える必要がありますが、中途半端に取り上げるのではなく、今回はあえて「典型的な公立小学校の姿」を記録したいと考えました。
日本で育ち、海外で生活する中で気付いたのは、日本の教育に当たり前のように存在する素晴らしさでした。
まずはその価値に自信を持ち、その上で課題と切り分けて考えるきっかけを作りたいと思ったのです。
日本にいると、「教育はうまくいっていない」という漠然としたネガティブな印象を持ちがちですが、海外から見ると異なる視点が見えてきます。
だからこそ、私が気付いたことを伝えたいと考えました。
フィンランドで拡大する反響、日本の教育が与えた影響
聞き手:フィンランドなど海外での反応はいかがでしたか。
山崎さん:2024年4月にフィンランドの劇場で公開された際は、最初1館のみでの上映でしたが、反響を呼び、最終的に20館まで拡大しました。
さらに、4カ月以上にわたり上映が続き、ヒット作となりました。
フィンランドは「教育大国」として知られていますが、本作を通じて自国の教育の未来を見つめ直そうとする動きが生まれたそうです。
日本の教育システムの光と影、大人に求められる責任とは
聞き手:教育の大切な側面を見つめ直す一方で、上履きがきれいにそろっているかの確認や、合唱時の姿勢を全員で揃える指導など、本当にそこまで必要なのかと感じる場面もありました。
山崎さん:良かれと思って始めたことが、いつの間にか行き過ぎてしまい、本来の目的を超えて厳格化してしまうことがあります。
そのような制度の危うさも数多く見えてきました。
完璧なシステムなど存在しないと改めて感じます。
コロナ禍では「マスク警察」や「村八分」といった社会現象が話題になりましたが、同じようなことが小学校でも見られました。
こうした現象は表裏一体であり、子どもたちは大人が作るシステムの影響を受けながら成長していきます。
そのため、教育の仕組みをどう進化させていくかは、大人の責任であると強く感じています。
映画を通じて教育を問い直す-日本と海外の視点から
小学校教育について考えるトークイベントが1日、東京都内で開催されました。
本イベントでは、映画をきっかけに日本や海外の教育の現状や課題について議論が交わされました。
フィンランドの大学を卒業し、教員経験もあるエルッキ・ラッシラ神戸大学助教は、同国で本作が注目された背景について言及しました。
フィンランドはOECDの学習到達度調査(PISA)でかつて1位を誇っていましたが、近年は順位が低下し、「個性を重視しすぎている」「学校の規律が緩すぎる」「教師の地位が十分に尊重されていない」といった課題が指摘されるようになっていると述べました。
また、「特別活動」に詳しい國學院大学の杉田洋教授は、日本の教育がエジプトやモンゴル、インドネシアなどで導入されている点に触れる一方で、日本の学校における集団意識の強さにも課題があると指摘しました。
山崎さんは「学級会は本来、合意形成を行う場ですが、その運営次第では“忖度”や“空気を読む力”を過度に求める場にもなり得ます。そのため、改めてその本来の意味を考える必要があるのではないでしょうか」と語りました。