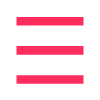2022年に離婚した夫婦のうち、同居期間が20年以上に及ぶ「熟年離婚」の割合は23.5%となり、統計が残る1947年以降で最も高い数値となりました。
離婚全体の件数は減少傾向にあるものの、熟年離婚の件数は依然として高い水準を維持しています。
専門家によると、高齢化に伴い「夫婦として過ごす老後の期間」が長くなったことで、人生の再設計を考える人が増えていることが要因の一つと考えられます。
情熱的なプロポーズを受けて結婚、当時は離婚なんて考えられなかったのでは。何十年も経つと気持ちは変わってしまうのでしょうか。
(※2024年8月13日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
離婚件数は減少、しかし熟年離婚は高止まり
厚生労働省が公表した2022年の人口動態統計によると、離婚の総件数は17万9099組(同居期間が不明の1万2894組を含む)で、減少傾向が続いています。
特に、件数が最も多かった2002年(28万9836組)と比較すると、約4割の減少となりました。
一方で、同居期間が20年以上の夫婦による離婚は3万8991組に上り、ここ20年以上にわたり4万組前後の水準で推移しています。
2022年における同居期間別の離婚件数を見ると、20年以上25年未満が1万6404組、25年以上30年未満が1万829組、30年以上35年未満が5192組、35年以上が6566組となっています。
最も多かったのは、同居期間5年未満の離婚で5万2606組(全体の3割超)でしたが、この件数や割合は年々減少傾向にあります。
こうした変化の背景には、人口減少に伴う婚姻件数の減少が影響していると考えられます。
長寿社会が影響か?増加する熟年離婚の背景とは
熟年離婚の割合が高まっている要因について、専門家は長寿社会の影響が大きいと指摘しています。
NPO法人・日本家族問題相談連盟の理事長であり、離婚カウンセラーでもある岡野あつこ氏は、「戦後から平均寿命が大幅に延びたことで、子どもが独立した後の夫婦の時間が長くなりました。その結果、性格の不一致などが原因で一緒にいることが難しくなり、新たな人生を歩もうと関係を見直すケースが増えています」と述べています。
2022年には熟年離婚の割合が過去最高となりました。
かつては夫の定年退職が離婚の大きな契機とされていましたが、近年では定年を迎える前の段階で「夫婦関係の危機」に直面するケースが増えていると専門家は分析しています。
役職定年が引き金に。収入減とモラハラで決断した熟年離婚の例
大手メーカーに勤める55歳の夫に対し、50歳の妻が離婚を切り出しました。
数年前のことです。
そのきっかけとなったのは、「役職定年」でした。
多くの企業で導入されている役職定年制度では、一定の年齢に達すると管理職の肩書が外れ、給与が減額されます。
妻から相談を受けた弁護士の堀井亜生氏によると、この夫も役職定年を迎えたことで年収がほぼ半減し、仕事への意欲を失い、情緒不安定になっていったそうです。
夫は老後の生活資金を試算し、「貯金がまったく足りない」と妻に怒りをぶつけるようになりました。
それまでの家計管理について細かく問い詰め、「俺はこんなに稼いできたのに」と暴言を吐いたり、時には暴力をふるったりすることもあったといいます。
妻は夫から渡される生活費をやりくりしていましたが、学費や住宅ローンの返済、夫の両親の病気による支出が重なり、思うように貯蓄ができなかったそうです。
一方で、夫は頻繁に飲み会やゴルフに出かけ、浪費が目立っていました。
子どもたちが独立することになり、夫と2人だけの生活には耐えられないと考えた妻は、家を出ることを決意しました。
妻の依頼を受けた堀井弁護士が、夫に対し婚姻費用として毎月の生活費を支払うよう請求しましたが、夫は「勝手に家を出たのだから払う義務はない」と拒否。
しかし、粘り強く交渉を続けた結果、月に十数万円の生活費を支払うことを認めました。
現在、妻はパートを続けながら別居を続けています。
離婚カウンセラーの岡野あつこ氏によると、熟年夫婦の離婚相談の7~8割は女性からのものだといいます。
その大きな要因の一つとして、夫のモラルハラスメントが挙げられます。
また、子育てが一段落したことも離婚を決断する要因となります。
退職金や年金などの財産分与を見据え、夫の定年の2~3年前から離婚の準備を始める女性も少なくないそうです。
収入減で対立、生活レベルの違いが引き起こした離婚例も
一方で、夫から離婚を切り出すケースもあります。
金融機関で管理職を務めていた男性は、57歳で役職定年を迎え、年収が3割減少しました。
当時49歳の妻とともに高級マンションで暮らし、子どもを私立中学や塾、習い事に通わせ、将来的には海外留学も視野に入れていました。
しかし、収入が減ったことで家計を見直したところ、子どもの留学費用だけでなく、大学費用の捻出も難しいことが判明しました。
そこで夫は「このままでは生活が成り立たないので、支出を見直してほしい」と妻に相談しましたが、妻は「収入が下がるのはあなたの努力不足で、私には関係ない」と拒否し、夫を無視するようになったといいます。
夫は家を出て、弁護士の堀井亜生氏に相談。話し合いの末、夫が養育費と学費を負担することで合意し、離婚が成立しました。
堀井弁護士は、「バブル世代は年収が右肩上がりであることを前提に消費行動をしてきたため、収入が減ると予想以上にショックを受け、配偶者との対立が深まりやすい」と指摘します。
その上で、50代に入る前に将来の収入減を想定し、家計を見直すとともに、夫婦で老後の生活について話し合うことが重要だと助言しています。