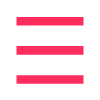大好きなアイドルやキャラクターを応援する「推し活」が、消費回復の鍵として注目されています。
この流れを支えているのは、10代後半から20代のZ世代です。
日本銀行の報告書でも、若者の消費意欲の高さを示す事例として昨年秋に初めて取り上げられ、今月9日に公表された最新の報告書にも掲載されました。
こうした旺盛な需要を受けて、「推し活」専用の専門店も登場しています。
リアルな恋愛もいいけれど、押し活は自分の生活の一部。
一昔前は「アイドルにうつつを抜かしているから結婚できない」と揶揄されたものですが、今の若い世代は価値観が異なるようですね。
中には押し活仲間同士で交際にいたったりすることも。これでプロポーズや結婚に
(※2025年1月11日 朝日新聞の記事を参考に要約しています。)
目次
「推し活」は生きがいそのもの。月20万円を費やす強者も
2024年11月9日の夕方、東京・JR池袋駅から徒歩5分の場所にある「推し活居酒屋 ○○の会」は、13部屋すべてが満室でした。
個室ののれんの向こうからは、楽しそうな歓声が次々と響いていました。
「かわいい!」「やばい!」
茨城県に住む会社員の女性(28)は、推している男性アイドルグループ「ダリア」のライブ前に、ファン仲間と2人で来店しました。
テーブルにはグッズがずらりと並び、ライブ映像やミュージックビデオを楽しんでいます。
料金は2時間の食べ飲み放題で税込み4,980円。
女性は1年前にライブを観て以来、「ダリア」に夢中になり、月に10回ほどライブへ足を運ぶこともあります。
会場では、推しが写った1枚1,500円ほどの写真を何枚も購入し、ライブ後にはメンバーと交流する時間も楽しんでいます。
チケット代を含めると、1回のライブで4万~5万円を使い、月に20万円に達することもあるそうです。収入の大半を「推し」のために費やす生活ですが、女性は笑顔でこう語ります。
「応援することが生きがいです。だからこそ、仕事も頑張れます!」
「推し活」専門居酒屋も登場。熱気あふれる空間
この居酒屋は昨年2月、「推し活」専用の店舗としてオープンしました。
運営するのは、医薬業界向けの冊子や印刷物を手がける「ベスト・プリンティング」(東京都港区)で、新規事業として展開しています。
来店客の95%は女性で、特に20代後半から30代の利用が多いそうです。
店長の上田瞬さん(34)は、「スーツケースいっぱいにグッズを詰めて来店する方もいて、推し活への熱意の高さを実感しています」と語っています。
若者が「推し活」に熱中する理由とは何なのか
調査会社ネオマーケティングが昨年3月に実施したインターネット調査によると、2万2,373人のうち1,803人(8.1%)が推し活をしていると回答しました。
男女別では、男性(5.9%)よりも女性(13.0%)の割合が高く、年齢層では10~20代(32.7%)が最も多く、年齢が上がるにつれて減少する傾向が見られました。
なぜ若者は推し活に熱心なのでしょうか。
ニッセイ基礎研究所の広瀬涼研究員は、
「終身雇用制度の崩壊や地域社会との関わりの希薄化により、若者は趣味を通じて社会とのつながりを求めるようになっています。推しに対して当事者意識を持ち、消費を通じて自分なりの意味を見いだそうとしているのです」
と分析しています。
また、Z世代に詳しい芝浦工業大学UXコースの原田曜平教授は、
「この世代はSNSを活用して多くの人とつながり、複数の肩書を持つことを好む傾向があります。推し活は、個性をアピールする手段のひとつではないでしょうか」
と指摘しています。
さらに、民間調査会社の矢野経済研究所によると、アイドルやアニメなど主要14分野を含めた2023年度の「オタク」市場規模は、推定約8,000億円に達すると見込まれています。
広がる「推し活」中高年にも浸透する応援文化
「推し活」という言葉はZ世代を中心に広まりましたが、同様の活動は中高年層にも根付いています。
現在の70~80代では、氷川きよしさんや純烈を熱心に応援するファンが多いことが特徴です。
川崎市に住む会社員の宮地正恵さん(48)は、歌手・吉川晃司さんのライブに2019年から再び通うようになりました。高校生の頃にファンだったものの、一時期足が遠のいていましたが、約25年ぶりにライブへ行くと、懐かしさと圧倒的なパフォーマンスに感動したそうです。
「後悔したくないという気持ちが強くなりました」と語り、エネルギッシュなステージから元気をもらっているといいます。
こうした「推し活」による消費の活発さに、日銀も注目しています。
昨年10月に公表された地域経済報告(さくらリポート)では、個人消費の動向を示す事例として、首都圏のサービス業の声が紹介されました。
「特に若者の『推し活』需要は旺盛で、グッズ販売が好調なうえ、客単価も上昇しています。
レジャー施設での支出も惜しまない傾向が見られます」と報告されており、2005年4月のさくらリポート創設以来、初めて「推し活」が取り上げられました。
今年1月の報告でも、「価格を引き上げても、推し活需要の高まりによりグッズ販売は堅調」(日銀名古屋支店管内の対個人サービス業)といった声が寄せられています。
日常の支出を抑える一方で、特別な体験には惜しみなくお金を使う「メリハリ消費」が定着しつつあると、日銀関係者も指摘しています。
物価高の影響で全世代の節約志向が強まる中、日銀は特に、賃上げの恩恵を受けやすい若者世代の消費動向に関心を寄せています。
高額支払いやトラブルも「推し活」には危険も潜む
推し活に熱中するあまり、トラブルに巻き込まれるケースも報告されています。
国民生活センターによると、高額なチケットを購入したものの入場できなかったり、別人の名前が記載されたチケットを買ってしまったりする事例が発生しているそうです。
また、ライブ配信で配信者を金銭的に支援する「投げ銭」をめぐるトラブルもあります。
2025年3月11日には、東京都の高田馬場駅付近で動画配信者(ライバー)と投げ銭をした視聴者の間で金銭トラブルが起き、殺人事件に発展してしまいました。
ある20代の男性は、昨年3月にライブ配信で特別なグッズを手に入れようと1万円分のポイントを購入しましたが、さらに追加購入を求められました。
断ると、「グッズを送らない」と言われたといいます。
さらに、未成年者が親の知らないうちに数万円以上を支払ってしまうケースも確認されています。
推し活に欠かせないSNSでは、アルゴリズムによって利用者が好む情報ばかりが流れる仕組みになっています
。芝浦工業大学の原田曜平教授は、
「この仕組みによって視野が狭まり、推し活にのめり込みすぎる人が増えている側面があります。サービスの提供側も、こうした問題を真剣に受け止めるべきです」
と指摘しています。